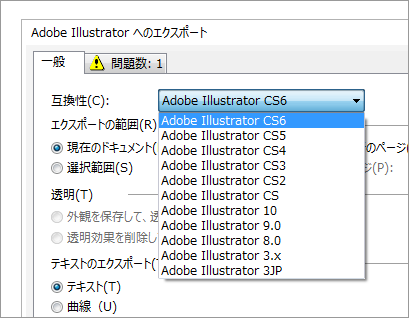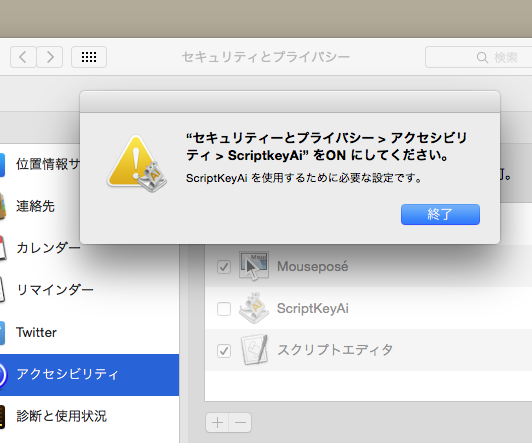公開ソフトをたまに整理することがありまして、ずっと放置している古いソフトはもう誰も使ってないよね~とダウンロードページから削除したりします。しかも、誰も使ってないから断りもいらないよね~と黙って勝手に削除します。そうしたところ、ComoとCiPTの問い合せをいくつかいただき、今もちゃんと使ってくれている方々がいることを教えてもらいました。
ごめんなさい!!
ということで、ダウンロードページにComoとCiPTを再掲載しました。どちらも2011年に公開したままのものです。
ちゃんとお手入れできるといいんですけど、今それをやると、当時できなかったあれもできるこれもできると欲が出て、結局収拾がつかなくなってぐだぐだになってやめて凹むんです。ここ数年ほんとにこんな感じ。多機能なアプリ作りも魅力なんですけど、機能がシンプルなものの方が私の身の丈に合っているみたい。で、2011年に公開したシンプルなものを(Yosemiteでも普通に使えていますし)そのまま使ってもらうのがベストと判断した次第です。